
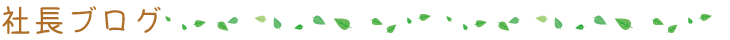
部屋を全部独立させて、廊下でそれをむすんでしまうと、旅館型間取りになります。
そこである部屋から別の部屋に行くには、部屋のドアを開けて廊下に出、
別の部屋のドアを開けて入る事になります。
もしそれが隣あった部屋なら、部屋と部屋の間の壁に出入り口をつければ、
いちいち廊下に出ないで部屋にすぐにいけるし、開けておけば部屋と部屋との生活が直結します。
どちらが便利かどちらがふれあいのある生活になるかは自明の理です。
動線という言葉をご存じの方も多いと思いますが、動線とは家の中で人がよく通る軌跡を指した言葉です。
たとえば、廊下や階段の事を動線部分とか動線スペースと呼んでいます。
旅館型間取りに部屋と部屋とを入り口で設けるとここにも動線がつくられてまわれる家になります。

家の中をもっと大きく回る
玄関から入ると、広がり家族空間、リビング+ダイニング+茶の間があります。
台所から洗面所、それからトイレを回って玄関に出られる部屋のつながりがあります。


敷地に余裕があれば理想の住まいは平屋と言われてます。 昔の日本の住宅は敷地に余裕があり殆ど平屋建てでした。 それは家の各部に行けるのに便利からです。 2階建てだと1階と2階が隔絶するからです。 ですが小さい家だと良いのですが、標準の大きさの家となると平屋が必ず良いとはいえません。 廊下が長くなり部屋相互のつながりが切れてしまい、部屋と部屋が遠くなるとやはり隔絶します。 住んで便利というのは日常的に生活している場所と部屋が出来るだけ近くつながり隣り合って居ることです。 リビングが日常生活の中心だったら、それに食堂や茶の間、座敷だの子供部屋だの、つながり隣り合うような間取りが可能でしょか? 中心の部屋が全部他の部屋で取り囲まれたら行灯部屋となり風が通らない日の入らない暗い部屋になります。 だから標準的な大きさの家は中廊下や片廊下回り廊下が出来てしまいます。 2階建てでも1階と隔絶させないで積極的につながりを持たせることが出来るのが吹抜けです。 吹抜けは2階の床を一部切り取り2階と1階の空間を縦に繋ぐことが出来ます。 リビングの上部の一部を吹抜けにすると、つながりあったり隣あったりさせたい部屋が2階にも取れる事になります。 建て売り住宅や住宅展示場の住宅にも吹抜けを取っているケースがありますが、玄関の上を吹抜けにした例が殆どです。 家を大きく見せようと言う魂胆が見え見えです。 冬などは寒いだけでです。 吹抜けをとるなら生活空間の一部に取るべきです。 吹抜けを挟んで2階に子供部屋があれば「1階からご飯ですよ」と上を向いて声をかければ 2階の窓から子供が顔をみせ、ばたばたと下りてくる、これこそが吹抜けの効用です。 1階と2階のコミニュケーションが吹抜けを通じて取れるのです。 子育て世代さんの家には大変有効です。 家族の気配が感じられる家になります。
8月14日に雨が☔️激しく降る中を故郷の能美島へ 墓参りに行って来ました。
8月13日に弟や次男がやはり雨の中を墓参り行きました。
次男に墓参りは欠かさぬ様に普段強く言っている手前 雨が激しく降る中を強行しました。 陸走では危ないと思い今回は往復フェリーを利用しました。
宇品港から三高港まで40分、そこから能美の沖美町まで車で20分です。 10時55分宇品港を出ました。 フェリーは墓参り客で車はぎっしりでした。
父方の親戚の墓所が3か所、母方が1か所、我が家と5か所お参りしまた。 雨続きのため盆燈籠は散々になった所が沢山見受けられました。
盆燈籠は浄土真宗でも安芸門徒だけの慣習です。
今年初めて塔婆にしました。 塔婆を6枚買いましたが、それぞれにご親切にマジックがついてました。 「気がきくのお」と思いきや水性マジックだった様で書いた名前が雨で流れて消えていきました。 墓参りを先に済ませ午後2時過ぎて能美の家で遅い昼食をしました♪ 雨で濡れたので風呂に入りました。 昨日次男に頼んでエコキュートの電源を入れて貰いました。
風呂自動を入れましたが時間が経っても湯がたまりません。 何回か繰り返しても少ししか溜まりません。 リモコンの液晶画面に風呂栓はしましたか? と出ます。 今年エコキュートにやり変えたので最近のは凄いのおと感心してました。
しかし風呂栓をしっかりしてなくてざあざあ湯が抜けてました。
頭が抜けてるので、こんなヘマをします。

帰りは16時5分の宇品港行きのフェリーに間に合いました。 帰りも殆ど満車でした。 やはり陸送よりフェリーの方が楽ですねー 辛抱人でフェリー代が勿体ないと陸送でしかも呉アライン使わず一般道で帰っていた 親父からは怒られそうですが?

三高港の待合室は新しく鉄筋コンクリート構造の3階建てで展望台つきの立派な施設が完成してました